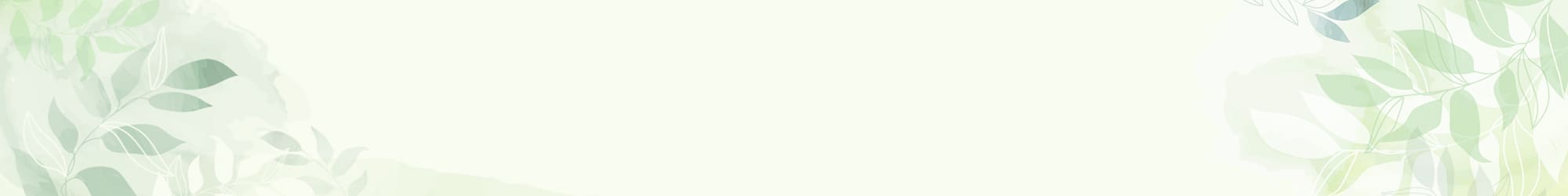
一般内科・生活習慣病
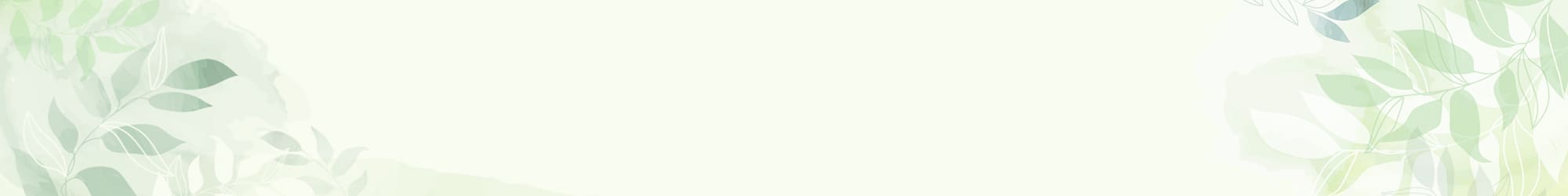
一般内科・生活習慣病

当院では内科全般の病気を幅広く診療します。日常生活の中で比較的生じやすい急な症状や生活習慣病など慢性疾患の診療を行います。
また、専門的な高度医療が必要と判断した場合は、専門の医療機関へ紹介し適切な治療を受けていただけるよう速やかに対応いたします。
複数の症状が出て「何科を受診したら良いかわからない」といった場合などお悩みの際にもお気軽にご相談ください。
このような症状がある方はご相談ください。
日常的に起こりやすい症状でも、適切な検査を行うことで重大な病気の早期発見につながることもよくあります。体調不良や健康に関して気になることがございましたら、何でもお気軽にご相談ください。
かぜは正式には「かぜ症候群」といって、咳、痰、のどの痛み、鼻汁、鼻づまりなどを主症状とする上気道(鼻やのど)の急性炎症の総称です。発熱、全身倦怠感、食欲低下などを伴う場合があります。
原因微生物の多くはウイルスと言われており、ウイルス性のかぜ症候群であれば、安静や水分・栄養補給により自然に治癒するため、ウイルスに効果のない抗菌薬は不要です。
当院では、咳や痰、鼻汁などを軽減する薬や解熱剤など症状に合わせて薬を処方します。
また、肺炎や気管支炎などの合併を疑う場合には、胸部レントゲンや採血など必要な検査を行います。
インフルエンザウイルスの感染症で、ウイルスには主にA、Bの2型があり、通常、寒い季節に流行します。感染してから1~3日間ほどの潜伏期間の後に、38℃以上の突然の高熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などが現れ、咳、鼻汁、のどの痛みなどもよく伴います。頻度は低いですが、肺炎や脳症などを合併することもあります。
当院では、迅速検査キットを使用し診断を行います。綿棒で鼻粘膜を拭って検査し、15分程度で検査結果が判明します。
感染性胃腸炎の原因微生物のほとんどはウイルス(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなど)で、一部に細菌(カンピロバクター、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌など)があります。ウイルスが付着した料理を食べたり、手指を口に触れたりすることなどで感染し、冬場に集団発生することも少なくありません。症状は嘔吐、下痢、腹痛、発熱などです。
当院では、症状に合わせて内服薬を処方し、細菌性と判断した場合には抗菌薬処方を考慮したり、脱水所見を認める場合には点滴したりします。脱水の予防が重要であり、自宅でできる経口補水療法の指導も行います。
生活習慣病とは、生活習慣が原因で発症する疾患の総称です。不適切な食生活や運動不足、喫煙、過度の飲酒、過剰なストレスなど、好ましくない習慣や環境が積み重なると発症リスクが高まります。高血圧症や脂質異常症、糖尿病、肥満症、動脈硬化症などを指します。これらは自覚症状があまりないため気付かないうちに進行し、様々な内臓や血管にダメージを与え、心疾患や脳血管疾患、がんなどの発症率が高まります。
そのため、異常を指摘されたり気が付いたりしたら、早期に生活習慣を改善することや治療すること、定期的に検査することなどが重要です。
日本高血圧学会では家庭血圧が135/85mmHg以上を高血圧としています(診察室血圧は140/90mmHg以上)。また、家庭血圧125〜134/75〜84mmHg(診察室血圧130〜139/80〜89mmHg)を高値血圧としています。これらを放置すると脳卒中や心臓病、腎臓病などの重大な病気を発症する危険性が高まります。
高血圧の多くは体質や生活習慣により生じますが、ホルモン異常などによって二次的に生じるものもあるため、当院では必要に応じて治療開始前に各種ホルモン検査を考慮します。治療としては生活習慣の指導や病態に応じた降圧剤の内服処方などを行います。
脂質異常症とは血液中の「悪玉」と呼ばれるLDLコレステロールや中性脂肪が増えたり、「善玉」のHDLコレステロールが減ったりした状態のことをいいます。この状態を放置していると動脈硬化が起こり、ゆっくり進行し、脳梗塞や心筋梗塞といった動脈硬化性疾患を生じるリスクが高まります。
糖尿病とは膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが十分に働かないため、血液中のブドウ糖(血糖)が増えてしまう病気です。1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病などがあり、日本人で圧倒的に多く、生活習慣病のひとつとされているのが2型糖尿病です。その発症には過食や運動不足、肥満、ストレスといった生活習慣が関係しています。
糖尿病を発症し進行すると、神経障害、網膜症、腎症、心疾患、脳血管疾患、がんなど様々な合併症を引き起こすことがあり、早期の治療介入が重要です。
当院での薬物治療としては内服薬処方だけでなく、必要に応じてGLP-1製剤やインスリン製剤の自己注射も行います。
TOP